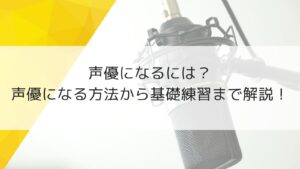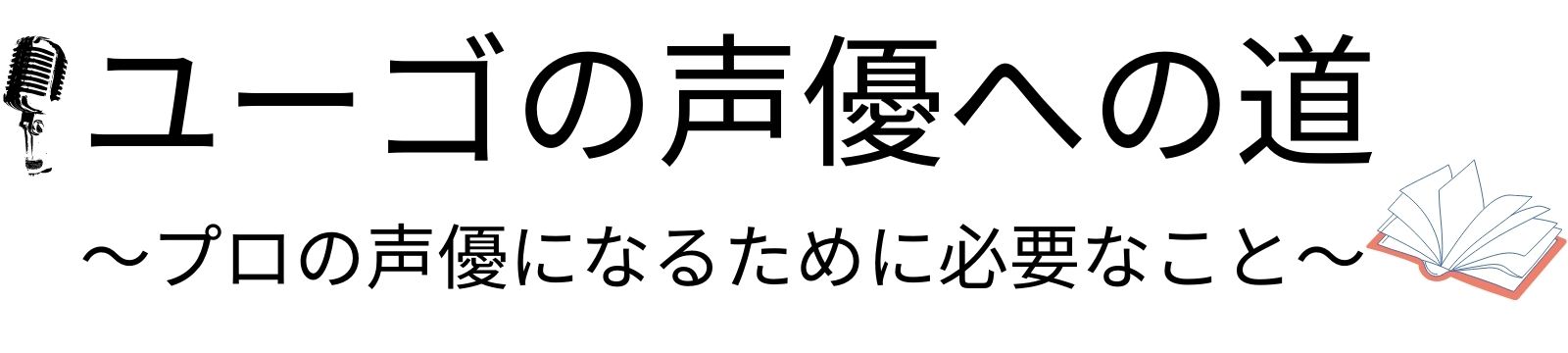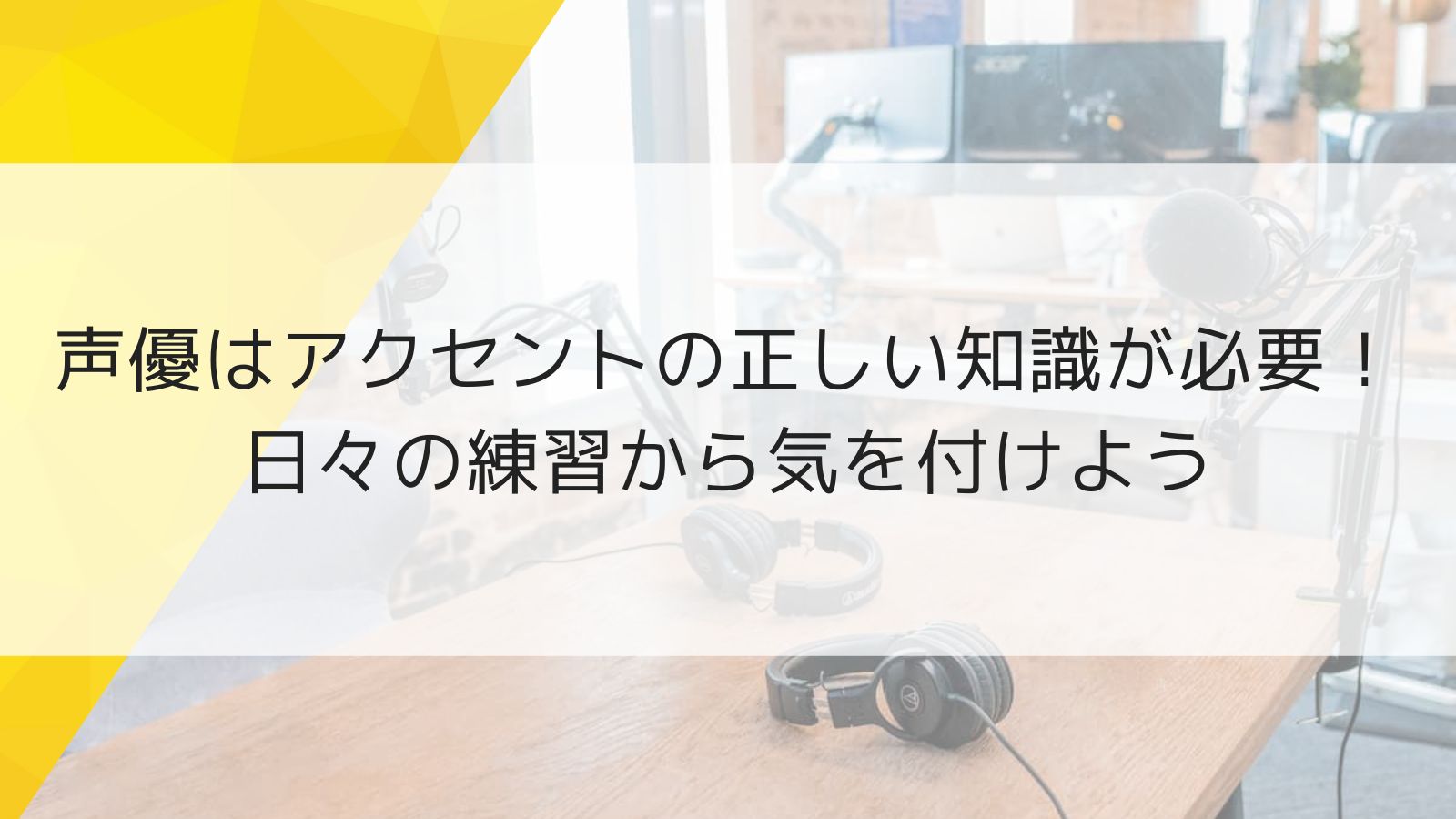「アクセント」は声優になるために必須の知識であり、基礎です。
しかし、多くの声優志望者が誤解していることがあります。
それは、正しいアクセントと知識は、勉強しなければ身につかないということです。
地方出身の人は「訛り」があるので、積極的にアクセント辞典で勉強をしています。
ですが、関東出身の場合、訛りが無いと勘違いし、アクセントの勉強を疎かにしている人がとても多いのです。
正しいアクセントと知識は、アクセント辞典で勉強しなければ絶対に身に付きません。
今回は、声優になるために必要な「アクセント」について解説していきます。
アクセント辞典の重要性
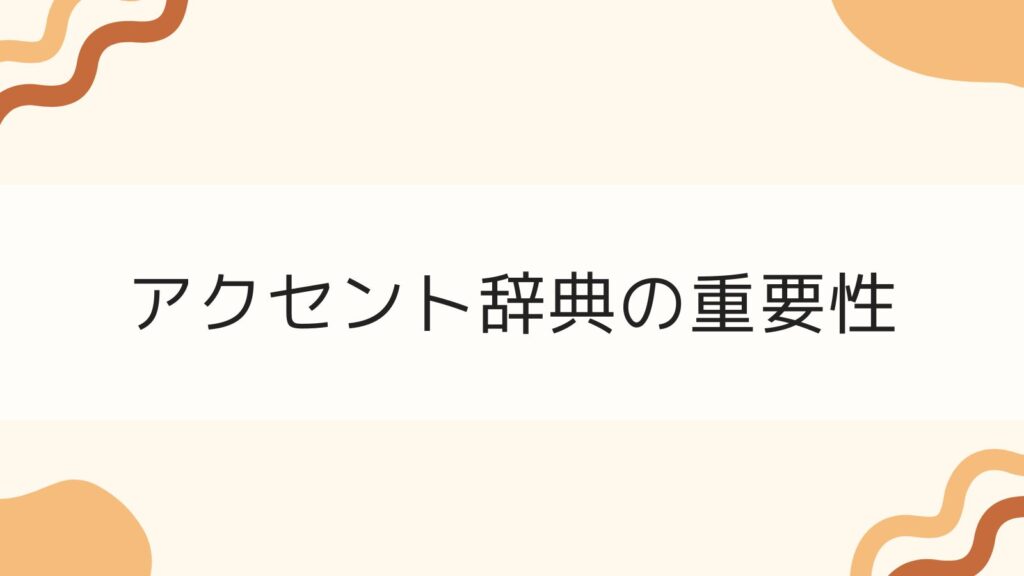
声優になるための必須道具といえばアクセント辞典です。
プロの声優になってからも必要なものなので、声優を目指す人は絶対に買いましょう。
地方出身の方は訛りを直さなければならないという意識が強いので、アクセント辞典で様々な言葉のアクセントを調べていると思います。
しかし、関東出身であっても正しいアクセントで日本語を話せていない人が実はとても多いのです。
自分は関東出身だからアクセントは大丈夫などと思っていると、後で痛い目を見ることになります。
実際私もそうでした。
演技を始めてから数年はアクセントについて気にしたことがありませんでした。
しかし、プロの声優に近づけば近づくほど、アクセントの重要性に気づくことになります。
早いうちからアクセントを気にするようにして、自分の耳を鍛えましょう。
まずはアクセントを普段から気にしてみてください。
そうすることで、日常会話やテレビで流れてくる日本語のアクセントに敏感になります。
気になる言葉があればすぐにアクセント辞典で調べていきましょう。
そうした日々の積み重ねで、正しい日本語のアクセントが身についていきます。
そして一番大事なことは、アクセント辞典に慣れることです。
アクセント辞典で調べ、アクセント記号を見て、正しいアクセントで日本語をしゃべる。
これができるようになれば、音の高低の感覚が養われます。
プロの声優で一番大事なことは、指定されたアクセントでしゃべれることです。
正しいアクセントでしゃべれることは当たり前です。
しかし、現場に行くと、このアクセントにしてと指定されることがあります。
作品の内容や、ディレクターによって、求められるアクセントが異なってくる場合があるのです。
一度指摘されたアクセントは、リテイク時には必ず修正できていなければなりません。
何度も同じダメを出されるようではプロとしてやってはいけません。
日頃からアクセントを気にして、音の下がり目に敏感になっていれば、アクセントを指摘されたときに即座に対応できるはずです。
それがプロの声優として当たり前のことと認識してください。
鼻濁音と無声化のルール
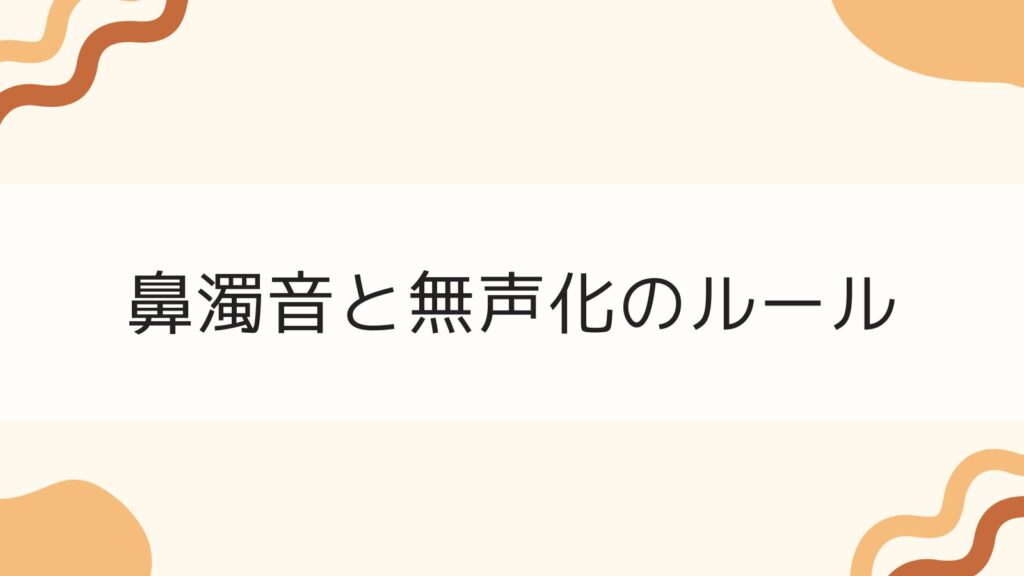
アクセント辞典には、鼻濁音、無声化について詳しく記載されています。
プロの声優であれば鼻濁音、無声化はできて当たり前のことです。
しかし、あなたは鼻濁音、無声化のルールについて、きちんと理解ができていますか?
実は、鼻濁音、無声化にはきちんとしたルールがあるんです。
○○な時に鼻濁音になる。
●●な時に無声化になる。
というようにルール化されており、それがアクセント辞典には明確に記載されています。
そのルールをきちんと理解し、適切に鼻濁音と無声化が使えるように練習しましょう。
この鼻濁音と無声化についても関東出身の人は油断しがちです。
プロの声優になりたいのであれば、地方出身の方と同じ意識で勉強する必要があります。
言葉を扱うプロになろうとしているのですから、最低限の基礎知識と基礎技術は、きちんと身につける努力をしましょう。
本のアクセント辞典を読もう
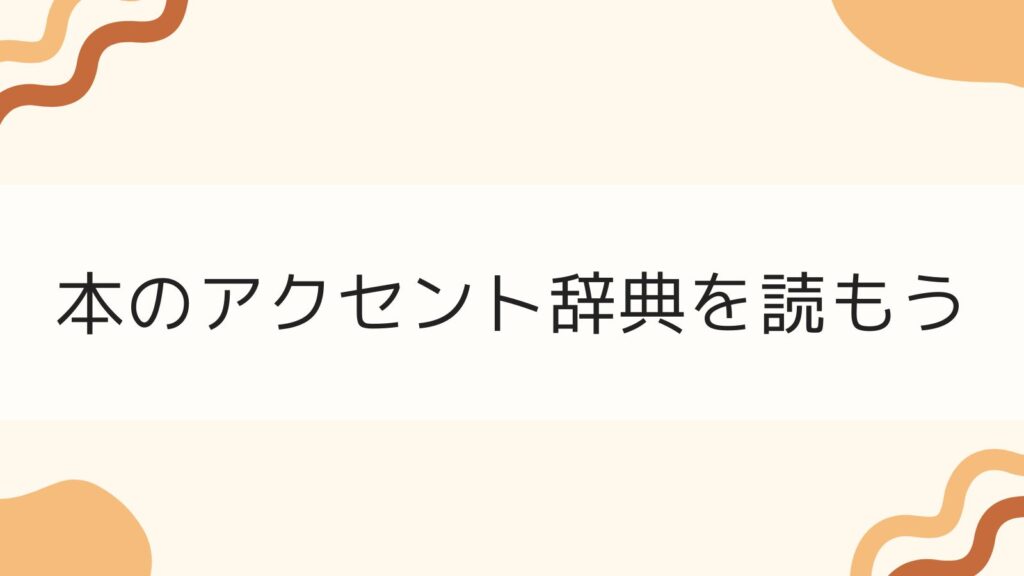
電子辞書でアクセント辞典を持っている人も今の時代は多いと思います。
ですが、電子辞書では単語のアクセントしか調べることができない場合があります。
もしあなたが電子辞書でアクセント辞典を使っているのであれば、一度確認してみてください。
実際に私が持っている電子アクセント辞典では単語のアクセントを調べることしかできません。
実は単語しか調べることができないのであれば、アクセント辞典としては不十分です。
本のアクセント辞典には「記号について」「辞典のきまり」「アクセントの解説」など、大事なことが文章で書かれています。
セリフは単語だけで構成されていません。
複合語になることで、アクセントに変化があります。
そして、単語に修飾語が付いた時も、アクセントの変化があります。
例えば「男の子」という言葉がありますよね?
音の低い部分を〇、高い部分を●で表します。
オトコノコ
〇●●〇〇
単独では上記のようなアクセントになります。
しかし、「この男の子」にするとアクセントは変わります。
コノオトコノコ
〇●●●●〇〇
アクセント辞典で単語を調べているだけではダメだという理由がここにあります。
アクセントは単語だけではなく、構成されている文、セリフで調べなければならないのです。
それについて詳しく書いてあるのが、本のアクセント辞典なんです。
助詞・助動詞の原則や鼻濁音、無声化の原則についても文章で明確に書いてあります。
あなたの電子辞書にそういった解説が載っていないのであれば、本のアクセント辞典を買う必要があります。
アクセント辞典の「記号について」「辞典のきまり」「アクセントの解説」などを、徹底的に読み込んでアクセントの原則を理解しましょう。
覚えることは難しいと思いますが、原則を知っていれば調べることができるようになります。
私は、本のアクセント辞典は持ち歩きに不便なので自宅で使うようにしています。
そして、現場やレッスンには電子辞書を持っていくようにしています。
細かく調べるのは自宅が多いと思うので、そうやって使い分けるのがおすすめです。
ちなみに私が使用しているアクセント辞典はNHKのものです。
恐らく、すべてのアクセント辞典に解説などが細かく載っていると思うのですが、私は他のアクセント辞典を持っていないので、断言はできません。
なので、この記事を読んでアクセント辞典を買うことを決意した人は、できればNHKのアクセント辞典の購入を検討してみてください。
まとめ
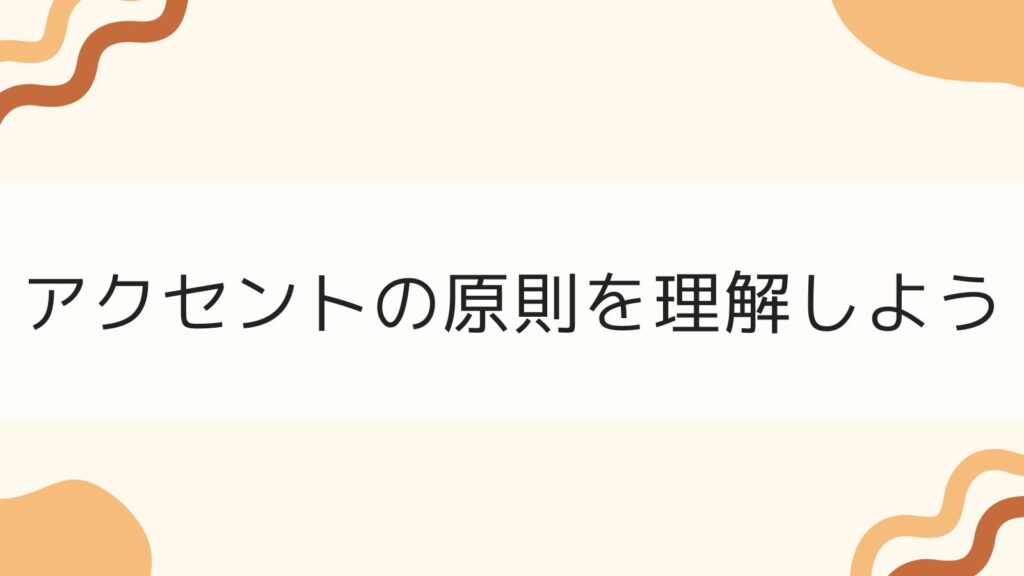
今回はアクセント辞典について書いていきました。
アクセント辞典は単語を調べるだけのものではありません。
文章として読む場合の原則について理解し、調べることができるようになることが重要です。
最初は時間がかかり大変だと思いますが、慣れていけば調べるスピードも速くなっていきます。
アクセントはあなたが思っている以上に指摘されることが多いものです。
そして、普段から気にしていない人の場合、指摘されてもわからない、直せないという状態に陥ってしまいます。
普段からアクセントには気を使い、耳を鍛えましょう。
そして、指定されたアクセントにすぐに修正できる対応能力を身につけてください。
現場ではアクセントに気を取られている暇なんてありません。
演技に集中するためにも、今のうちにアクセントはしっかり勉強しておきましょう!